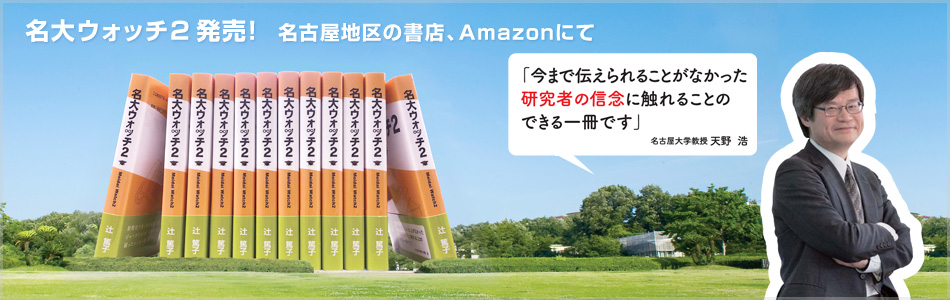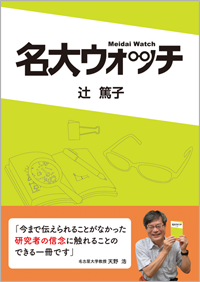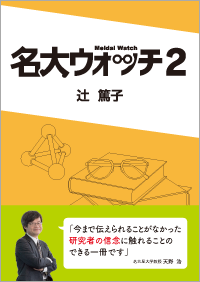2018年03月27日
「女性研究者よ、幸せであれ」
3月末で定年退職した未来材料・システム研究所の楠美智子教授は、名古屋大学の工学系で唯一の女性教授だった。大学時代の恩師に「あなたはがむしゃらさが足りない」と言われたこともあり、「はっきりした意思を持って続けてきたというより、この分野が好きでなんとなく続けてきたという感じが強い」と振り返る。子育てのために2度、研究を離れた。しかし、その都度、請われて研究現場に戻ってきた。カーボンナノチューブやグラフェンなど炭素でできた新素材の研究で実績を重ね、民間の研究所から名古屋大学に転じ...

 RSSを購読する
RSSを購読する