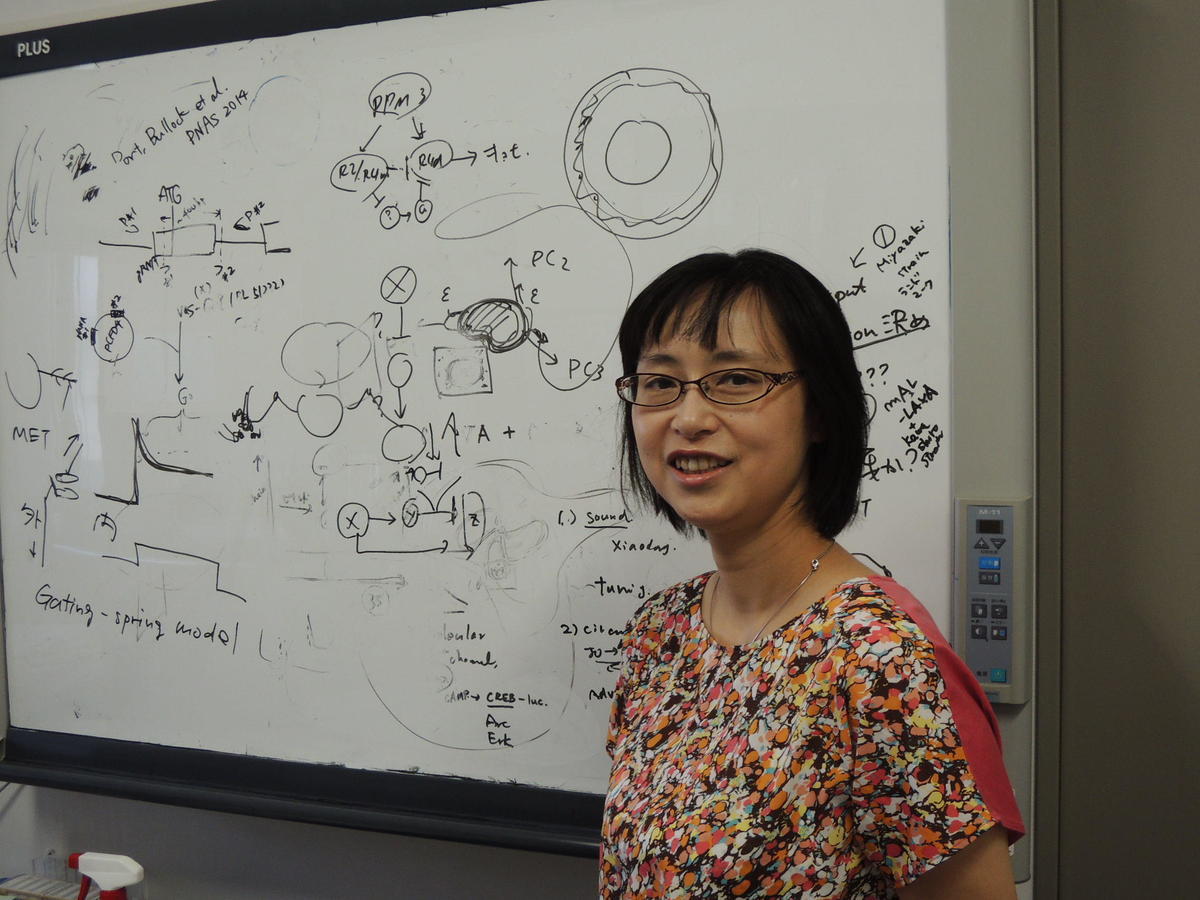2017年07月18日
30代半ばの女性教授誕生の背景
名古屋大学理学研究科では、30代半ばで教授に就任した女性2人が活躍している。全国を見渡しても、まず例のない若い女性教授だろう。そもそも男性でもこの年代で教授になることは珍しいが、名大では若くして教授になる例がある。職位にとらわれずに交流ができる自由な雰囲気に加え、「女性の名大」といわれるだけのさまざまな努力も背景にあるのだろうか。その中には、女性に限定した採用枠という思い切った手立てもあった。
女性限定の公募によって2011年に採用されたのは生命理学専攻の上川内あづさ教授だ。当時36歳。東大で薬学の博士号を取得した後、ドイツ留学などを経て、東京薬科大の助教を務めていた。「教授職に応募しようなどとはまだ思っておらず、女性限定公募ということで初めて自分を候補者として意識しました」と話す。もし、女性限定でなければ、このとき応募することはなく、先延ばしにしていただろうという。
この枠は、PIと呼ばれる教授など独立した研究者の採用をめざす、全国でも初めてのものだ。採用された女性にはまず、大学が人件費などを負担し、5年以内に正規のポストに移ることになっており、あいた分は次の採用枠に当てる仕組みだ。いずれ正規のポストに就く以上、選考は通常の公募と変わらない厳しさで行われる。女性枠で採用されるなら、おそらく通常の公募枠でも採用されるに違いない。それでも、女性限定というだけで、通常の公募ではまずないような大勢の応募がある。
上川内さんは自身のことを振り返り、「なぜ女性枠だから応募しようと思ったのか、その思い込みは何だったのか、自分でもよくわからない」というが、一般的に男性の方が自己評価が高い、つまり女性は自分を過小評価しがちなことが背景にあるかもしれない。
そして今、応募を受け付ける側になってみて、女性の応募者がきわめて少ないことを改めて実感しているという。むろん、女性研究者そのものがもともと少ないことがある。上川内さんが所属する生命理学専攻の森郁恵教授は、そうしたなかで女性を増やすには「分野を絞らず、優秀な研究にこだわる人事」が重要だという。対象分野が狭ければ、該当する女性はきわめて少なくなるが、広げればそれだけ人材のプールも大きくなる。
地震学者であるロバート・ゲラー東大名誉教授は7月12日付日経新聞の「大学国際化の課題」と題したインタビューで、外国人が増えない原因として「採用基準が曖昧で、自分の弟子や仲間だけが条件に当てはまるようにしている。外部に優れた人材がいても確保できず、大学がタコツボ化している」と手厳しい指摘をしている。女性研究者の採用にも共通する面がありそうだ。タコツボだと数の少ない女性が入るのは難しい。米マサチューセッツ工科大でも、理工系の女性教員を10年でほぼ倍増させた際、人材を広く求めることで水準を保ったとしていた。
いずれは女性限定の枠など不要になるときがくるだろうし、早くそうなってほしいと思う。しかし、現状ではこうした枠は一定の役割を果たしていると言っていいだろう。
一方、上川内さんは、女性の応募が少ない背景には、女性特有の課題もあるのではという。結婚して子どもがいる場合、女性は子どもを連れていくことが多く、それだけ負担も大きくなる。上川内さんは東京に夫を残して1歳の長女と名古屋に赴任し、その際、一人暮らしだったお母さんもついてきてくれた。名大には学内保育園、そして全国で唯一の学童保育園もあり、今は小学生になった長女が通っている。さまざまな子育て支援態勢があることが、名古屋への子連れ単身赴任を決める際に背中を押した。単身赴任をしている教員の子育てネットワークでの助け合いも大きい。地方の大学に赴任した夫とは別居が続いているが、ショウジョウバエの聴覚を手がかりに、脳の仕組みを解き明かす研究に没頭する毎日だ。
若くして教授になったもう一人は物質科学国際研究センターの唯美津木教授で、2013年、34歳だった。専門は触媒化学、東大で博士号を取得し、岡崎市にある分子科学研究所の准教授から、通常の公募によって選ばれた。分子研時代に結婚した研究者の夫も幸い、名古屋大学に職を得た。もうすぐ3歳になる長男と3人暮らしだ。
女性がポストに就く場合、配偶者の処遇はこれからの大きな課題だ。欧米では配偶者のポストも用意して招くことも多いが、日本ではまだまだ。実際、名大でも海外から女性を教授に招こうとしたが、夫の希望がかなうポストがなく、断念したことがあったそうだ。
それにしても、若くして教授という責任あるポストに就くのは大変な面もありそうだ。唯さんにそう尋ねると、「年齢にかかわらず、大変なことは大変。というより、大変でない、ということはない」という返事が返ってきた。博士課程を2年で中退して助手になったときは、自分の研究の一方で学生の指導にも当たり、「本当にしんどかった」。労せずに優秀な学生が集まって実験をしてくれた東大時代から一転、分子研時代はアジア諸国を走り回るなど学生集めに苦労し、「自転車操業」だったという。それでも、じっくり考える時間を持てたので新しいテーマを見つけ、それを名大で大きく展開することになった。
「研究は時間の勝負で、常に競争にさらされている。子育てとは両極端なので、気持ちの切り替えが大変」という。家に帰ったら、長男が寝るまではメールを見ないと決めている。現在は、兵庫県にある大型放射光施設SPring-8 を使って、燃料電池触媒の劣化の問題などに取りくんでいる。そのための出張もあり、「今は海外にはなかなか行けません」。
「私は海外へは行かない。必要なら名古屋に来い、という気持ち」。そういうのは、先に登場した森郁恵教授だ。生命理学の大先輩である岡崎恒子名誉教授、郷通子名誉教授(現、名大理事)に次ぐ世代のパイオニアで、この春、名大大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センターを創設し、そのセンター長となった。線虫やショウジョウバエなどの小動物を使って脳の機能解明をめざす神経科学の国際的な拠点として世界に名乗りを上げたのだ。
これまでの歩みは、当然のことながら女性であることに深くかかわっている。米国で大学院生としての研究生活を伸び伸びと送って帰国後、女性ゆえ、大変な思いをして逃げだそうと思い詰めたこともあった。助教授として名大に来たのは1998年、2004年に教授になった。心に決めていたのは「男性のサイエンスのやり方に迎合しない」ことだ。研究で実績を上げる一方で、女性研究者が活躍できるための環境作りにも時間と頭脳を割き、女性リーダーを育てるための合宿なども行ってきた。
2006年の段階で、生命理学専攻には森さんと助教とで女性はたった2人だった。11年に上川内さんが教授として加わり、ほっとしたという。「怖い人、堅苦しい人と思っていたけど、本当はざっくばらんなんですね」といわれるようになったのもそのころからだ。無意識のうちにずいぶん身構えていたのだと気づかされたそうだ。今や生命理学専攻の女性教員の比率は約4分の1である。
世界拠点作りの構想は、上川内さんをふくめ3人の女性研究者で日頃話す中から生まれた。「失うものはない」と本気になり、実現に向けて文字通り姦(かしま)しく奔走したという。森さんが女性研究者のための環境作りに力を注いできたことが、本来の目的である研究面での飛躍につながった形だ。森さんによれば、子育て環境の整備も決して福利厚生事業ではなく、「研究力強化」が目的なのだ。「女性教員の増加によって、既に教授になって研究室も軌道に乗っていたわたし自身の発想力が上がったことに自分でも驚いています」と森さんは実感を語る。
米科学誌「セル」のエミリー・マーカス編集長も朝日新聞のインタビュー(7月6日付)で「論文の執筆者に女性が増えたことで、科学への視点がより多様になり、研究の内容が強くなっているという印象がある」と語っている。
これからの科学のためにも、もっともっと多くの女性が伸び伸びと活躍できる環境づくりが必要なのだと思う。

 RSSを購読する
RSSを購読する