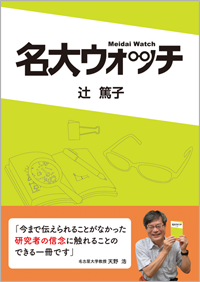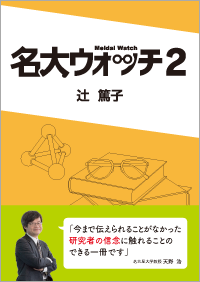2017年07月28日
世界の若者が集う自動車工学のメッカ
「名大の自動車工学は世界的に関心の的、インドでも有名になってきましたよ」
東京大学のインド事務所長を務める友人の言葉だ。自動運転が注目される今、「世界一のトヨタ」のイメージが名大と重なっている面もありそう、とも言うが、「名大の自動車工学」の看板が光っているらしい。インドの最高学府インド工科大の教授の息子も昨年、名大に入学したという。
自動車工学の看板は工学部ではなく、英語で講義を受けられるグローバル30プログラムの一つとして掲げられている。看板が掲げられていなくても、その中身は機械工学を始め、工学部のさまざまな学科で教えられていることはいうまでもないが、やはり「ナゴヤの自動車工学」の看板のアピール力は大きいということだろう。
その看板のアピール力を実感する機会があった。夏期集中プログラム「自動車工学における先端技術と課題」(Nagoya University Summer Intensive Program, 略称NUSIP)である。海外からの学生を対象にしたプログラムで、受講料は2000ドル、旅費なども加えれば個人負担はおそらく50万円くらいになる。それでも希望者は多く、毎年約2〜3倍の競争率になるという。私費でこれだけの参加者が集まるプログラムはちょっと珍しそうだ。2008年に始まり、今夏でちょうど10年目を迎えたこのプログラムの成功が、グローバル30での自動車工学の開講にもつながった。
きっかけは、米ミシガン大工学部と協定を結んでいるのに、もっぱら名大生がでかけて行くばかりで先方からはあまり来ない、このアンバランスを是正するために何かできないかという議論が工学部内で起きたことだった。浮上したのが、名古屋という地域の強みでもある自動車工学を中心としたサマープログラムだった。産業としても勢いがあり、東海圏にはトヨタ、ホンダ、スズキといったメーカーに加えてデンソーなどの関連企業も多い。工場もある。こうした企業では卒業生が活躍しており、名大とのつながりも強い。講義は名大の教授陣と、企業の専門家が受け持ち、自動車工学の基礎から最先端までをカバーすることになった。むろんすべて英語、参加資格は学部3年生以上と大学院生だ。ミシガン大学など提携校を中心に、他の大学にも広げていった。当初から携わっている石田幸男特任教授によれば、「企業の第一線の専門家を含め、これだけの講義がまとまって聞ける場所はちょっとほかにはない」。参加者はどんどん増え、現在の定員は40人、希望者が多いために1校当たり3、4人までに絞ってもらうようにしているそうだ。
 自動車市場の動向について、企業の専門家の講義を受ける(7月7日、工学部で)
自動車市場の動向について、企業の専門家の講義を受ける(7月7日、工学部で)
今年は6月14日から7月20日までの6週間だった。海外からの参加者は37人、在籍する大学で見ると、米国の9校から20人、イギリスの1校と香港の2校から5人ずつ、カナダの2校から3人、イタリアの1校から2人、スウェーデンと中国が1人ずつと、実に国際性豊かな顔ぶれだ。中国、台湾、あるいはインドなどアジア各国から欧米の大学へ留学している学生も多く、講義をのぞいてみると、半分くらいはアジア系という印象だった。女性は7人で、2割弱を占める。名大工学部の女子学生は1割弱だからその2倍になる。
オリエンテーションの後、プログラムは京都、奈良への旅行から始まった。日本の文化に触れてもらうことも大きな目的なのだ。名大に戻り、午前中は日本語の授業、午後は設計・製造からデザイン、安全性、さらには市場動向や将来像まで、名大の教員と企業の専門家による自動車に関わる広範な講義だ。毎年、特別講義もあり、今年はドイツ・ボッシュ社の日本法人の役員が不確実な今日の世界における挑戦について語った。2010年にはトヨタの豊田章一郎名誉会長もクラスに参加して学生たちと議論した。
見学ツアーでは、トヨタ、三菱自動車、スズキ、横浜ゴムなど近隣の工場に加え、東京方面にも出かけて自動車会社や公的な研究施設を見学した。通常ではまず見学できない場所もある。企業が異例ともいえる対応をしてくれるのは、名大とのつながりもあるだろうが、それ以上に、「学生たちは企業にとって金の卵だから」と石田さんはいう。つまり、海外の一流大学で機械や電子工学などを学んでおり、高額の自己負担があっても参加したいという意欲と日本への関心がある学生たちだからだ。しかも、程度の差はあるものの、日本語も話せる。例年、2割程度の学生は日本語を学んだ経験があり、初めての学生も6週間にわたって連日学ぶので、簡単な会話はできるようになる。
 参加者全員がそれぞれのテーマでプレゼンを行った(7月20日、工学部で)
参加者全員がそれぞれのテーマでプレゼンを行った(7月20日、工学部で)
各自がまとめのプレゼンをした後、最終日の20日には締めくくりの懇親会が開かれた。全員が日本語でスピーチした。たどたどしい学生もいたが、「一生の思い出になりました」「忘れられない経験ができました」「先生、お世話になりました。本当にありがとうございます」「サヨナラはいいたくない」「また会いましょう」などと、口々に感謝や思い出を語った。学生たちの面倒を見てきたエマニュエル・レレイト講師は「学生たちはこのプログラムで非常にいい経験をして、最後はすっかり打ち解けていい友人になったと思う」と話す。自身、ケニア出身で異文化交流に力を注いでいる。
インド出身でカナダのカルガリー大学の2年生を終えたばかりのガンセラ・パンカジさんは最年少の19歳、「企業の人の話も聞けてすごくよかった」と言う。「いい意味でスローでステディな日本流のやり方が大好き」だそうだ。イタリアのマティナ・トッチさんはローマ・ラ・サピエンツァ大学で機械工学を学ぶ女子学生、エネルギーに関心があり、「プログラムに参加して多くを学ぶことができた」という。
彼らにとって、得がたい経験をし、世界の友人に出会った貴重な6週間だったことは間違いない。過去の参加者の中には、名大のグローバル30や大学院、あるいは日本の他の大学に進学した学生もいるそうだ。「日本企業にもぜひ就職してほしい」というのが、石田さんの願いだ。
そして、もう一つ、石田さんの当初からの大きな願いがある。若者があまり海外に出たがらないといわれる中、できるだけ多くの名大生に、国際化のきっかけとして役立ててほしいということだ。その思いから、このプログラムには10人の名大生向けの枠が設けられている。海外からの学生とともにすごすことで、いながらにして国際的な環境に触れられる。駅前留学ならぬ、学内留学である。しかも、名大生なら無料だ。
ところが、残念なことに、名大生枠の参加者のほとんどは留学生で、日本人学生は毎年1,2人にとどまる。英語で講義を受け、毎回レポートを提出し、最後にプレゼンをする、というのは、英語に自信がない学生にとってはハードルが高いのかもしれない。
今年、日本人学生として唯一の参加者は、修士課程1年の小林義典君だった。学内のポスターでプログラムのことを知ったが、工学部3,4年生のときは忙しくて参加できなかった。英語には自信がなかったが、車が大好きで参加を決めた。彼を「ヨシ」と呼ぶ友人たちも世界にできた。「普通なら見られない所も見られるし、メッチャ面白くておいしいプログラム」と後輩たちに参加を勧める。
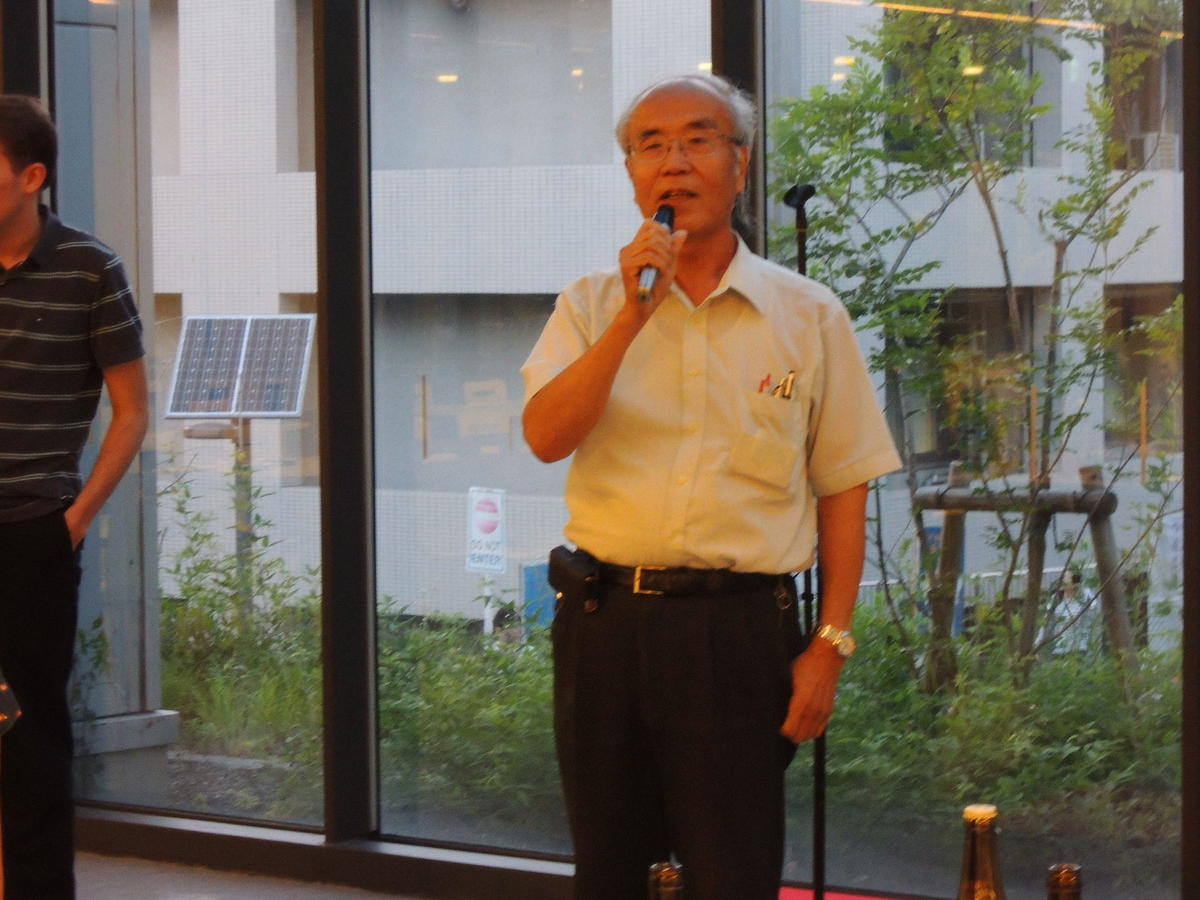 学生たちの感謝の言葉にこたえて挨拶する石田幸男特任教授(7月20日)
学生たちの感謝の言葉にこたえて挨拶する石田幸男特任教授(7月20日)
夏の1ヶ月余り、キャンパスの一角にできるせっかくの国際ゾーンだ。もっと生かされていい。石田さんは懇親会の最後に、「ここに来たくて来られなかった仲間たちのことも考えてほしい」と語りかけたが、海外からの学生は選考をくぐり抜け、多額の自己負担もいとわずに暑い名古屋にやってくる。そこまでして来る価値のある学びの環境があるということだ。名大生もそこに参加することで、自らが学ぶ環境を見直すことになるのではないだろうか。また、これからの新しい時代を、あるときは競い、あるときは協力しながらともに生きていくことになる同年代の学生たちと交流することは、視野を大いに広げ、未来への資産になるに違いない。旅費もいらない。小林君がいうように、こんなおいしいチャンスを逃す手はない。1,2年生は、このプログラムに参加することを目標に、英語の勉強に励んではどうだろう。
石田さんは毎年、オリエンテーションの折などに参加を呼びかけているが、なかなか参加者が増えない現状に、たとえば名大内に国際ゾーンを作り、そこのレストランなどでは基本的に英語以外の使用を禁止するなどの思い切った方策が必要では、という。
学生たちを見ながら、浮かぶ言葉があるという。高杉晋作が20歳のときに記した。
「翼あらば 千里の外も飛びめぐり よろづの国を 見んとぞおもう」
大学はまさに、さまざまな意味で翼を用意してくれる場所なのだと思う。存分に利用して大いに羽ばたいてほしい。

 RSSを購読する
RSSを購読する