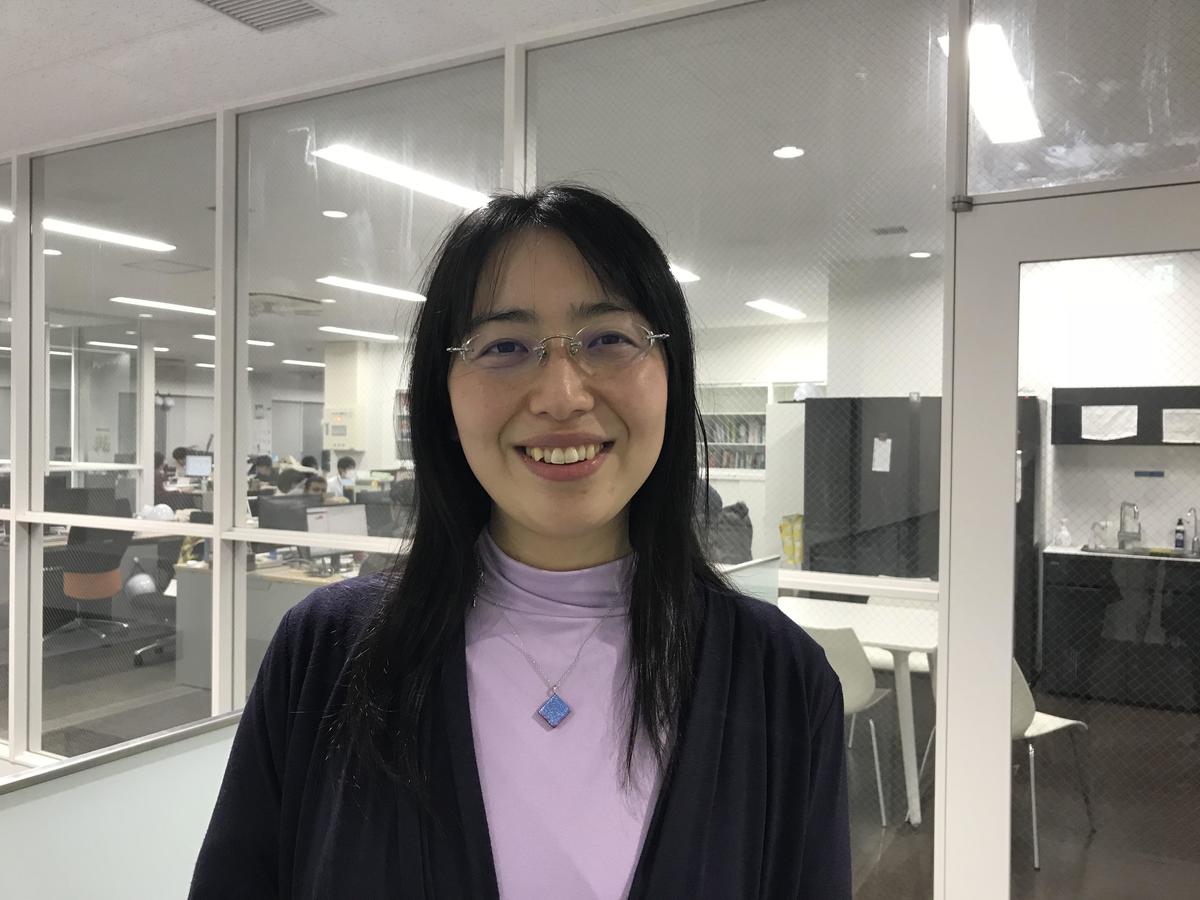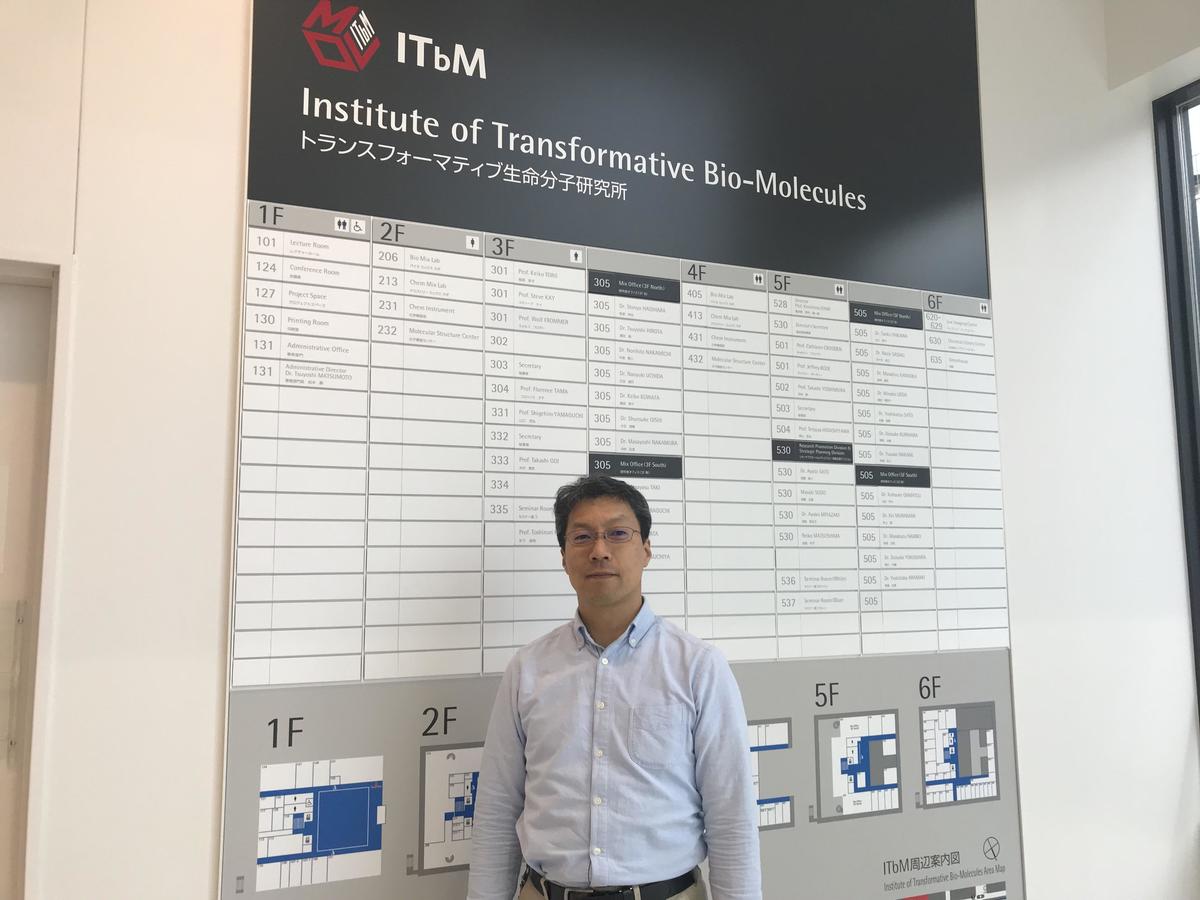2018年05月01日
博士の多彩な能力を生かす
博士といえば研究者、というイメージを抱く。だが、博士には研究をするだけではない、さまざまな役割がある。名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)を訪ね歩きながら、改めて感じたことだ。ITbMは分子をキーワードに異分野を融合させた研究を進め、大きな成果をあげていることを先に紹介した。そのユニークな研究活動は、直接研究をするわけではない博士たちの活躍あってこそ、であり、その意味で彼らは研究者と対等のパートナーなのである。
昨今盛んに報道されるように、博士を取り巻く状況は厳しい。文部科学省の科学技術・学術政策研究所が2月末に発表した「博士人材追跡調査」第2次報告書でも、民間企業での雇用は伸びず、アカデミアでも特に理学系では安定した雇用が得られにくい現状が指摘されている。社会人や留学生ではない課程博士は修了時にその6割が学資金などの借り入れを抱えているという調査結果もあった。こうした現実を反映してか、博士課程入学者は2003年度の18232人をピークに2016年度までに3000人以上減ってきている。
だが、高度人材としての博士はこれからの日本社会にとって極めて重要であることは間違いない。博士たちがその能力を発揮できる場を広げていく必要がある。その方策の一つが博士のキャリアパスの多様化だ。
かつて米国で科学報道に携わっていたとき、博士たちが狭い意味の研究だけではない、さまざまな場所で力を発揮している様子を見て、日本との違いに驚いたことがある。ジャーナリストから議会スタッフ、博物館にベンチャー企業まで、専門性を生かしながら働いている博士にあちこちで会った。例えば銀行にも博士がいて、学会などをまめにのぞいて研究の動向を知り、それを投資の判断に生かすのだと聞き、同様のことが日本であるだろうかと思わされた。
もっとも、話を聞くうち、日本の博士が狭い分野での特化した専門家というイメージがあるのに対して、米国での博士はむしろ「広い」、いろいろな課題に取り組む力がある存在だとされており、そもそも博士の教育に違いがあることも痛感した。
ITbMの宮﨑亜矢子・特任助教は英国のインペリアルカレッジで化学を学んだ博士で、海外も含めた広報を担当している。ロンドンでの学生時代を振り返り、「博士課程の友人たちは、医学部に進んだり、地下鉄に就職したり。そのまま大学に残った人はほとんどいなかった」と話す。自身は帰国後、メーカー勤務を経て、科学技術振興機構(JST)の研究プロジェクトの一員になり、ケミカルバイオロジー分野の研究をしていたときに誘いを受け、ITbMに転じた。当初は、研究もしていたが、両立が難しくなり、現在は主に広報活動をしている。
自分の研究が社会に役立つところまでを見たいと思いつつ、基礎研究ではその実感を持ちづらかった宮﨑さんにとって、広報の仕事は、得意分野を生かしながら社会と関われる魅力があるという。10歳のときに帰国して苦労した経験から、異なる文化をつなぎたいという思いもあった。科学の世界のワクワク感にしても文化の違いにしても、人々が知らないことは多い。それを世界に伝えて共有してもらう、そんなキャリアパスを描きつつあるという。自ら手を動かして実験する研究活動から離れる寂しさ、そして将来への不安を感じていた時期もあったが、進む道を思い定めた今、そんな気持ちは吹っ切れたという。
宮﨑さんをITbMに誘ったのは、JSTの同じプロジェクトのメンバーだった佐藤綾人・特任准教授である。拠点長の伊丹健一郎教授が、ITbMを作り上げるうえで最大の功績者と讃える一人でもある。
佐藤さんは名大の天然物化学で学位を取り、京大でのポスドクを経て理化学研究所でJSTの研究プロジェクトに参加していた。そんな折、当初は行く予定のなかった学会の懇親会で、伊丹さんと「運命的出会い」をした。名大で顔見知りだった伊丹さんに、これから研究拠点を立ち上げるので研究推進の仕事をしてくれないかと誘われたのだ。実はその時点ではまだ最終審査の前で、拠点が文科省に採用されるかどうかもわからなかった。にもかかわらず、佐藤さんは二つ返事で「行きます」。進路を迷っていた時でもあり、新しい仕事に興味が湧いたのだが、即答した自分に自分でも驚いたという。
ITbMにおける研究推進とは、研究者の発想を社会実装につなぐまでのサポートをすることだ。研究者が研究に専念できる環境づくりに加え、広報活動も含まれる。基礎研究にも関与するなど、いわゆるリサーチ・アドミニストレーター(URA)より仕事の幅は広そうだ。伊丹さんは、新しい研究組織の枠組みを考えていた時、研究者でも事務職でもない、こうした機能を担う新しい職種が不可欠だと思っていたという。研究者のマインドを持ち、しかし、研究以外にいろいろな能力を持った人たちが支援してくれたら、研究者は研究に専念できる。特に異分野の融合となれば、未経験の課題もたくさん出てくるからなおさらだ。そういう人たちは適切な環境さえあれば大活躍してかけがえのない存在になる、という確信もあった。そんな一人として頭にあったのが佐藤さんだった。学会で偶然会ったため、まだ申請中ながら、リクルートした。
 研究推進部門のトップとして最も忙しい一人、佐藤綾人特任准教授
研究推進部門のトップとして最も忙しい一人、佐藤綾人特任准教授
伊丹さんから見た佐藤さんは興味が広く、次々に出てくるアイデアを人とコミュニケーションしながらさらに広げていく特殊な才能がある。「これは面白そう」「あれも面白いんでは」と周りの研究者を巻き込んでいく。境界領域で新しいことを始めるのにうってつけの人材だった。
ITbMの一つの特徴は、専門の違う研究者が一つ屋根の下にいるミックスラボだ。だが、現実には、分野が違えば、また日本人と外国人では、簡単には混じり合わない。佐藤さんは、話をしながら、研究のサポート役もしながら、異分野融合が進む環境を整えていった。伊丹さんの期待に応え、研究推進部門の責任者としての職責を十二分に果たした。
それに加え、佐藤さんにはもう一つ、伊丹さんから託された「生物学者を分子の虜にする」というミッションがあった。分子をキーワードにして生物学と化学をつなぐのがITbMの理念だったが、実際には生物学者たちは自分の研究に分子の力が必要だとは思っていなかった。そこで、各自のテーマに合った作用を持つ分子を「マイ分子」として全員に持ってもらい、それを使えば何がわかるか、分子の力を実感してもらうのが狙いだった。佐藤さんは、研究に役立ちそうな機能を持った分子をあちこちから集めて来てライブラリーセンターを作り上げた。狙いはズバリ、生物学者たちは見事に分子の虜になった。この結果、ITbMでの研究が進む基盤ができた。
虜になった一人が、植物の気孔を専門とする木下俊則教授だ。ライブラリーを駆使し、分子を使った気孔の制御へと研究はガラリと変わった。4月初めには気孔が開くのを抑える新しい化合物を発見、佐藤さんたちと共同で発表した。この物質を植物の葉にかけると、しおれにくくなることも確かめた。食糧の増産や切り花の鮮度保持など、実用面での可能性も大きく、国内外の企業との共同研究も進めている。
一方、研究所の運営の面で伊丹さんが100%信頼し、頼りにするのが、事務部門長の松本剛特任教授だ。もともとは、伊丹さんの隣の研究室の助教だった。本人は2回断ったというが、抜群の事務処理能力と運営能力では衆目の一致するところだった。どんどん外堀を埋められ、最後に「ほかにだれかいるか」と言われ、そこまで言われるならと引き受けたという。最初は、1日の半分でいい、という話もあったようだが、むろん、そういうわけにはいかない。
研究から離れたことで、「プレッシャーがなくなって気が楽になったのが半分、やはりちょっとつまらないなというのが半分」という。
研究者の心理や行動パターンもわかった事務部門長の存在は極めて大きいと、皆が口をそろえる。「こっち行こう、いやあっちだ、などというのは得意だけど、きちんと整えることは苦手」という伊丹さんは、「おかげで研究に専念できる。研究をしなければ自分の価値はゼロだと思っているのでありがたい」と話す。
佐藤さんや松本さんのように、戦略的に研究を支援する仕事はこれからますます重要になるはず、と伊丹さんはいう。これからさらに大きな役割を果たして欲しいと伊丹さんは期待している。
伊丹さんが「運命のような縁を感じる」というのが、戦略企画部門で知財や企業との連携などを担当する須藤正樹特任准教授だ。伊丹さんとは京大の同じ研究室出身の同期生だ。製薬企業のファイザーが研究所を閉鎖した際に創薬ベンチャー企業ラクオリア創薬の立ち上げに加わり、同社が名大東山キャンパスにオフィスを構えたことからITbMにもよく足を運んでいた。ある時、別の会社に移ることを決めた須藤さんが挨拶のために訪ねてきた。伊丹さんたちは研究成果を外につなぐために企業の経験者がいてくれたら、という話を内部でしていたところだった。彼しかいない、そう直観して、「40代を一緒に全力疾走しようぜ」などと言って口説いた、と伊丹さんは振り返る。須藤さんは決まっていた転職先を断り、ITbMに移った。
今は、国内外の企業とITbMの研究者をつなぐ仕事を進めている。企業が考えることがわかるので、企業と大学をつなぐいわば通訳としての役目を果たしたいという。先に挙げた気孔の研究をめぐる企業との連携も須藤さんが手がけた。
通訳といえば、生物学と化学をつなぐという、ITbMの根幹となる部分で重要な役割を果たしているのが、ライブイメージングセンターの佐藤良勝特任准教授だ。リベラルアーツ教育で知られる国際基督教大学で生物学を学び、その後、博士号を取った。生体内での分子の動きをとらえるための顕微鏡などを整備して、ITbMだけでなく、全国の研究者に使ってもらうための支援をするのが仕事だが、その一方で、化学者側から生物学に橋をかける役割でスカウトされた多喜正泰准教授とのコンビで、それを生物学側で受け止める役目をしている。佐藤さんは帰り際に必ず階下の多喜さんのところに寄り、「あれが見えたら面白いのでは?」などと二人で議論するのが日課だ。ここで多くのテーマが決まっていくという。
佐藤さんは、研究支援は日本では単なるお手伝いのように思われがちだが、ユーザーとともに考えて、いい研究になるのに少しでも力になれたらうれしい、と話す。一方で、自分のテーマを持ち、細々でも研究を続けたいという。誰も見たことがない現象を、顕微鏡を通して自分の目で見ることはこのうえない幸せだからだ。
 生物学者の佐藤良勝特任准教授(左)と化学者の多喜正泰特任准教授、両分野をつなぐ名コンビだ
生物学者の佐藤良勝特任准教授(左)と化学者の多喜正泰特任准教授、両分野をつなぐ名コンビだ
ITbMのユニークな融合研究は、研究現場を知る博士たちの多様な働きによって初めて可能になり、支えられてもいる。博士の働き方という点でも、新たなモデルを示しているといえそうだ。新年度に入り、ITbMの10年のプロジェクト期間も残り4年を切った。切り拓いてきた世界をさらにどう発展させるのか。ITbMのこれからに注目したい。

 RSSを購読する
RSSを購読する