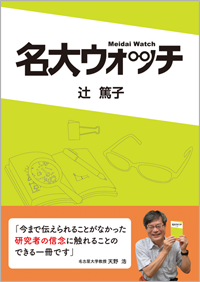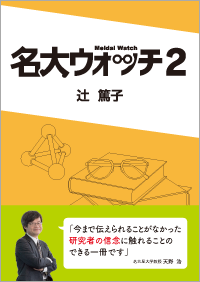2019年12月06日
ミャンマーから先人に思いを馳せる
名古屋大学大学院医学系研究科の濵嶋信之教授は10月末、ミャンマーの旧首都ヤンゴンから車で約4時間、ジョビンガウッ郡の農村にある病院を訪ねた。ベッド数50、地方の小さな私立病院だが、はるばる訪ねたのは理由がある。この病院は、名大大学院で医療行政を学んだ卒業生によって2013年に設立され、地域医療の新しいモデル作りをめざしている。実情を視察し、今後の支援に役立てるのが訪問の目的だ。 名大が力を入れるアジア諸国での人材育成の中で、人々の生命に直結する医療は重要な分野の一つだ。育っ...

 RSSを購読する
RSSを購読する